2018年08月06日
| 病院名 | 近江八幡市立総合医療センター | 設立母体 | 公立病院 |
|---|---|---|---|
| エリア | 近畿地方 | 病床数 | 407 |
| 病院名 | 近江八幡市立総合医療センター |
|---|---|
| 設立母体 | 公立病院 |
| エリア | 近畿地方 |
| 病床数 | 407 |
| コンサルティング期間 | 4年間 |
滋賀県近江八幡市にある市立病院、近江八幡市立総合医療センター(407床=一般:403床、感染症:4床)。地域包括ケア病棟の導入で、急性期一般入院料1の最重要要件である重症患者割合を満たすとともに、高回転・稼動の病床管理を実現。年換算で7200万円の増収に結びつけました。入院医療の最適化を目指した施策でも、病棟看護師の残業時間を大幅に削減するなどの成果を出しています。経営改革を推進した現場スタッフに取材するとともに、改革をリードしてきた宮下浩明院長(兼病院事業管理者)にお話を伺いました(本記事は2018年時点の記事です。直近の高度急性期の取り組みについてはこちらをご覧ください)。

右下から時計回りで、木下明美副院長兼看護部長、宮下浩明院長、診療情報管理士の田邊智氏、医療技術部長の鈴木博人氏、湯原、経営企画課の北川博也課長補佐、地域包括ケア病棟担当師長の片山千鶴子氏、メディカルソーシャルワーカーの川端美甫氏、地域包括ケア病棟前担当師長の奥野かおる氏、地域包括ケア病棟専従理学療法士の原田昌宜氏
東近江圏域の医療の質、安全を担保しつつ、経済性にも考慮しながら、地域の人々が医療難民にならないよう、急性期医療の提供体制維持・発展に邁進している近江八幡市立総合医療センター。2017年度の病床稼動率は92.2%、平均在院日数は9.6日と、高回転・稼動の病床管理を実現しています。一日平均入院患者数は375人、一日平均外来患者数は899人、救急受診患者数は年間1万5893人となっています。
グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)が同院のコンサルティングを開始したのは、2015年7月。GHCと滋賀医科大学医学部附属病院看護部が共同主催した「看護必要度勉強会」に、当時の看護部長が参加されたことが、コンサルティングをご利用される直接的なきっかけになりました。

近江八幡市立総合医療センターの外観
コンサルティングを開始したのは、入院収益の約4割を占める入院基本料が、「急性期一般入院料1」に相当する当時の「7対1入院基本料」へ昇格したばかりの時。ただ、現状のままでは今後も7対1入院基本料の施設要件を満たし続けることは困難と考えていました。
当時を知る経営企画課の北川博也課長補佐は、「激変しつつある医療提供体制の中で、当院が今後、どのような立ち位置や方向性を目指すべきか、明確に見通せない状況だった」と振り返ります。
7対1入院基本料の維持が難しい最大の理由は、外部の後方連携先が少なかったことです。7対1の高回転な病床管理を維持するためには、亜急性期患者の受け入れ先を確保することは絶対条件。さらには、自病院を急性期にシフトするため、回復期リハビリテーション病棟を閉じたことも、長期入院患者が増え、重症患者割合(当時の7対1入院基本料の施設基準は15%)が低下する一因になっていました。
そのため、中長期的な観点から7対1入院基本料の維持を考えると、いち早く自病院の立ち位置を見直し、病床再編などの改革に踏み切る必要性がありました。そこで院内の関係者が議論をしつくし、(1)機能分化(2)入退院支援室の設立(3)集患の強化――の大きく3つの戦略を導き出しました。ここでは(1)の機能分化に的を絞ってご紹介します。
機能分化は、地域包括ケア病棟の導入を軸にしました。ただ、今でこそ急性期病院が地域包括ケア病棟の導入を検討するケースが増えてきましたが、当時はまだ極めて前例が少ない時期。急性期病棟のスタッフが、地域包括ケア病棟で仕事をすることへの抵抗や、本当に機能させることができるのかという懸念も気になるところでした。「単科で活躍してきた看護師が混合病棟で務まるのか」「現状のリハスタッフの人員体制で機能させることができるのか」――などの懸念です。
地域包括ケア病棟を運用する「地域包括ケア病棟チーム」の立ち上げに、リハビリテーション部門から最初に加わったリハビリテーション科で医療技術部長の鈴木博人氏は「とにかく、立ち上げ当初は『(地域包括ケア病棟の施設基準である)リハビリの必要な患者に対して1日平均2単位以上のリハビリ実施』を守れるかどうかに、毎日ひやひやしていた」と振り返ります。そのため、リハビリの前日実績を毎朝確認し、その数字を見える化した上で、施設基準をクリアしながら急性期病棟のリハビリにも対応できる体制の維持に苦心してきました。

鈴木医療技術部長
看護部門は、看護師の配置に頭を悩ませました。今の地域包括ケア病棟は、回復期リハビリテーション病棟を急性期病棟に変更した経緯があり、何度も病棟を変更しているため、部内の理解が得られない懸念もありましたが、副院長兼看護部長の木下明美氏は「なぜ地域包括ケア病棟が今必要なのか」「具体的にどういうことをしていけばいいのか」などを示す資料を作り込み、関係する看護師一人ひとりへ丁寧に説明していきました。

木下看護部長
導入には多くの懸念もあったため、院内全体と各診療科への十分な事前説明と、導入前の「模擬病棟」運用を実施。2016年10月からの地域包括ケア病棟導入に向けて、6~8月の3か月間、転換予定の急性期病棟を、地域包括ケア病棟であると想定して運用しました。地域包括ケア病棟の導入は、院内横断の多職種連携での取り組みが不可欠。こうすることで、導入当初のインパクトを最小限に抑えるとともに、実際に運用しないと見えてこない課題なども抽出することができました。
円滑な院内横断の多職種連携を実現させた立役者の一つとして、地域包括ケア病棟候補患者抽出システムと地域包括ケア病棟閲覧システムの2つのシステムで構築された「通称:「田邊システム」の存在があります。
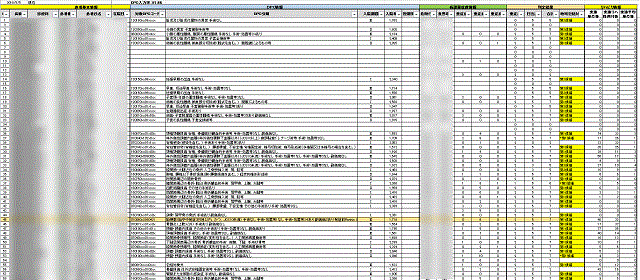
「田邊 システム」のイメージ(写真は抽出画面にモザイク処理をしたもの)
田邊システムとは、同院の診療情報管理士である田邊智氏が開発した、DPCデータや看護必要度データ、FIMデータなど地域包括ケア病棟の運営に欠かせない情報を一覧できるシステム。病床管理を担う管理職が一同に介し、毎週2回開催される「病床運営会議」では、この田邊システムを用いて、地域包括ケア病棟へ入棟する患者も含めて、病床管理の詳細について決定していきます。

田邊診療情報管理士
院内、どのパソコンからもこの田邊システムにはアクセスできるため、関係者は病床運営会議以外でも、病床管理に必要な情報を入手したり、関係者との調整をしたりすることができます。地域包括ケア病棟の担当師長である片山千鶴子氏は、「週明けは特に空床が出ることも多く、随時、田邊システムで情報を確認し、空床が出ないよう各病棟と連絡し合っている」としています。田邊システムは円滑な病床管理をするための仕組みとして機能しているほか、個々人の能力を最大限に引き出すシステムとしても機能しています。

片山地域包括ケア病棟看護長
同院の支援を担当するGHCマネジャーの湯原淳平は、「この病院の最大の強みは、スタッフ全員のモチベーションが非常に高く、スタッフ同士の仲がいいこと」と説明します。「地域包括ケア病棟チーム」の立ち上げメンバーである看護師長の奥野かおる氏(現在は医療安全担当師長)とメディカルソーシャルワーカーの川端美甫氏は、「はじめてのことで戸惑いも多かったが、いつでも一人ではなく、他職種のチームでやっていることに加え、いつでも上長が相談に乗ってくれたので、心強かった」と口をそろえます。

川端社会福祉士
院内では第三者の立場である湯原の存在も有効活用しました。628人の正規職員がいる同院において、すべての職員の意見が一つになることはほぼ不可能。院内の関係者だけで意見がまとまらない場合、第三者の立場からの意見を活用することは効果的です。リハビリテーション部門からの専従の理学療法士として、地域包括ケアチームで活躍する原田昌宜氏は、「訪問時に毎回行われるコンサルタント講演が、現場のスタッフがやりやすい空気を作ってくれる」と指摘します。

原田理学療法士
403床ある一般病床の一部である48床を地域包括ケア病床へ転換した同院は現在、一般病床を維持し続けていた場合と比較して、月間600万円の増収となっており、年換算すると7200万円の増収につながりました。当然、急性期一般入院料1も維持し続けています。
スタッフ同士の信頼関係を軸に、入念な準備と独自のシステム、個々人のモチベーション、第三者の立場などをフル活用してきた近江八幡市立総合医療センター。地域包括ケアシステムの実現に向けた課題は山積みで、地域医療構想調整会議や診療報酬改定ごとに新たな課題が出てくると思われますが、それを乗り越える力の源が「チーム力」であることに、変わりはなさそうです。
宮下院長にGHCのコンサルティングを振り返っていただき、どのようなメリットがあったのか、また、高いチーム力を維持し続ける秘訣などをお聞きしました。
――湯原のコンサルティングについてご感想を教えてください。
宮下院長:外部からの声は、組織の内部を動かす極めて有効な手段だと感じています。例えば、いくら当院の事務系職員がDPC制度の知識を極めたり、これからの医療界の流れを先読みしたりしても、その声を内部の職員に届けるには、限界があります。

宮下院長
やはり、GHCという病院コンサルティングで名が売れている会社のスタッフが、さまざまなデータを示し、プレゼンテーションすることの価値は大きいです。「自分たちは変わらないといけないのかもしれない」という行動変容を引き起こすきっかけにつながります。
特にGHCの一番いいところは、他の医療機関の状況と比較分析できるベンチマーク分析。このステップを踏まえることで、根性論や感情論から離れて、一気にロジカルな改革プランを打ち出し、そのゴールに向けてスタッフ全員で走り出すことができるようになります。
また、ベンチマークは「外の空気を感じる」というメリットもあります。一部の医師は、医療機関を転々とし、外を知る機会もありますが、特にコメディカルは新卒で入職し、外を知る機会なく仕事をしているケースも多い。そのため、データを通じて他の医療機関の状況を知ることは、井の中の蛙になることを防ぐことにもなりえます。
地域包括ケア病棟立ち上げに伴う病床再編や、入院医療の効率化が目的の「PFM(Patient Flow Management)センター」を運用する患者総合支援課の立ち上げなど、いくつかの大きなプロジェクトを推進できているのは、院内のスタッフたちが外部のコンサルタントの声を通じて、「なぜ、それをやる必要があるのか」という意味を十二分に理解してくれたからだと感じています。
ただ、外部の話を鵜呑みにせず、地域の特性に合わせてアレンジし、常に手直ししながら進めていくという姿勢は必要だと思っています。
――地域包括ケア病棟の立ち上げはご苦労されたと聞いています。
宮下院長:大変なプロジェクトではありましたが、早い時期に素早く対応できて良かったです。都会と地方都市では急性期病院の役割は全く違います。当然、地方都市にある当院が高度急性期一本というわけにもいきません。国が提唱する「地域包括ケアシステム」という考え方にもっと踏み込み、実践していく必要があると感じています。
今後は自病院の機能分化にとどまらず、地域との連携をもっと深めていく必要もあるでしょう。そうして地域包括ケアシステムの実現に向けて邁進していかなければ、地域を守れる医療提供体制を維持、存続させていくことはできないと考えています。
――PFMセンターについてはいかがでしょうか。
宮下院長:立ち上げて約1年半立ちますが、患者はもちろん、スタッフからも好評です。中でも、病棟看護師の残業時間が劇的に減っています。患者のアセスメントをPFMセンターが担っているので、これまで病棟で1~1.5時間かかっていたアセスメントが15分くらいに減少しています。ほかにも、外来診療をする医師の負担軽減、予定手術の中止件数減少などの効果が出ています。
――湯原は、貴院の最大の強みとして、高いチーム力を挙げます。
宮下院長:あまり意識したことはありませんが、11年前の病院移転が影響しているのかもしれません。病院移転は、全員団結しないとできない大事業だったためです。これを乗り越えたということは、一つの要因ではないかと感じます。
もう一つは、普段からスタッフ一同、お互いに多様性を認め合う、リスペクトし合うという文化が根付いています。病院ですから、多様な職種や性格の人たちが一緒に働いています。ただ、価値観や目指す目標というのは、「患者のために」というところで共通しているはずです。ですから、一口に経営改革と言っても、単に「診療単価を上げる」では、現場は動かない。病院、特に急性期病院は、人の人生の中で特別な場所であり、決して生活する場所ではありません。ですから、常に「患者のために」を意識し、「早く家に帰す」ことを目指していれば、それが在院日数の短縮につながり、それは今の医療制度の流れとも合致しているので、例えばPFMのように、収益はきっと後からついてくると考えています。
――本日はありがとうございました。
| 湯原 淳平 (ゆはら・じゅんぺい) | |
 |
コンサルティング部門シニアマネジャー。看護師、保健師。神戸市看護大学卒業。聖路加国際病院看護師、衆議院議員秘書を経て、GHC入社。社会保障制度全般解説、看護必要度分析、病床戦略支援、地域包括ケア病棟・回リハ病棟運用支援などを得意とする。日本経済新聞や週刊ダイヤモンドなどメディアの取材協力も多数。総務省 経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー。 |
Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.