-
Services
Hospital Management - Consulting Services
Publications
- Our Consultants
- Case Studies
- About Us
-
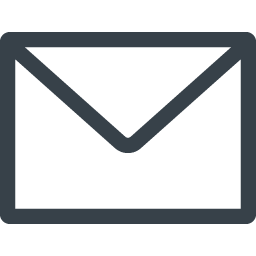
2011年03月24日
| 病院名 | 那覇市立病院 | 設立母体 | 公立病院 |
|---|---|---|---|
| エリア | 九州地方 | 病床数 | 470 |
| 病院名 | 那覇市立病院 |
|---|---|
| 設立母体 | 公立病院 |
| エリア | 九州地方 |
| 病床数 | 470 |
| コンサルティング期間 | 1年間 |
沖縄県の温暖な気候のなかで約30年間、地域の患者さんのために医療を提供し続けてきた那覇市立病院は、2008年に地方独立行政法人となりました。それ以来、積極的に民間病院の経営手法を取り入れ、医療の質の向上をめざしています。グローバルヘルスコンサルティング(以下、GHC)が同病院のコンサルティングをスタートしたのは、2010年4月。数多くの病院の手術室カイゼンを手がけてきたGHCマネジャーの相馬理人がコンサルティングを実施。分析結果の可視化によって動き出した病院改革の様子について同病院の副院長であり手術室運営委員会委員長の久高弘志先生にお話をうかがいました。(文中、敬称略)
ー GHCにどのような印象お持ちですか?
久高弘志先生 GHCにコンサルティングをお願いして、一番良かったことは、他病院とのベンチマークがみられたことです。データで自病院の手術件数がまだ十分でないことを知ることによって、改善へのモチベーショも高めることができました。手術件数を増やすことができない原因は、患者数にあるのではなく、手術室の運用に問題があることはわかっていましたから。
ー これまでにも手術件数を伸ばす努力をされたことはあったのですね?
久高弘志先生 県内の病院に比べると手術件数が少ないということはわかっていたので、外科系の医師にはそうしたアナウンスをしていたのですが、現場の立場からしてみると「手術室に入れないから件数が伸びない」という主張だったのです。そこで4年前に、手術件数を増やすために、手術室を6室から8室に増室したことがありました。財政的にも無理して行ったのですが、手術件数は思うように増えませんでした。その後は、他の病院と比べて具体的にどこが悪いのかがわからないため、管理する立場としてもなかなか強くいえず、改善は思うようにすすんでいませんでした。
ー 手術室は増えたけれども、手術件数は改善されなかったのですね。
久高弘志先生 そうです。当院には麻酔科のマンパワーなど、比較的人的な余裕はあったのです。それでも手術件数が増えなかったので、なんとかしなきゃならないと考え、手術室の分析をしてもらったところ、手術室が考えていたよりもまだ十分に稼動していないことがデータで明らかになりました。
相馬理人さん 定量分析フェーズを経て、定性調査を行わせていただく中、各診療科において、手術待ち患者は存在しており、ボトルネックがどこにあるのかはっきりして参りました。
ー GHCの分析結果から具体的にどのようなことがわかったのでしょうか。
久高弘志先生 まずは、実証分析により現状に対する共通認識を得たことです。GHCも同席された会議の場でも、1日に行っている手術件数についての現場の主張が、実データで示された分析結果で否定される場面などもありました。客観的な評価結果から、効率化、カイゼンに対するコンセンサスを得たうえで、入室時間の繰り上げや入れ替え時間の短縮、そして、各科の実績に応じた手術枠の最適化などを行ってまいりました。
ー 院内でそうした改革をすすめていくうえで反発などはなかったのでしょうか。
久高弘志先生 はじめは、協力的ではないスタッフもいましたが、現場スタッフが考えていた数よりも手術室が稼動していないデータをみせたことによって、反発していた人間の納得も得ることができました。
ー ベンチマーク分析の結果をみせることによって、納得していただけたのですね。
久高弘志先生 医療人は向上心が強い人が多いと思います。ですから、他病院との差を知ることによって、負けたくないという意識が働いたのだと思います。また、手術室の運用を見直したことによって、手術が非常に組みやすくなりました。それまでは、午前中に手術をやって、お昼休みをとって午後の手術という流れでしたが、現在は午前中の手術が終わり次第、出来る限り速やかに手術を入れています。そうすることによって時間外が少なくなるうえに緊急手術が入れやすくなりました。
相馬理人さん プロジェクトを進める中、手術室カイゼンの目的が、“手術を必要とする地域の患者をいかにして受け入れていくことが出来るか?!”にベクトルが揃ってきたように感じていました。
久高弘志先生 それまで胆のう炎の手術は、予定手術として組んでいました。その場合、早くても1週間後になってしまいます。胆のう炎の手術適応からいうと、緊急手術でできない場合は、3ヵ月後に手術することになっています。そうすると別の病院に行ってしまうケースが多かったのですが、そういったケースが少なくなりました。また、大腿骨の骨頭骨折も手術前までの入院期間が他病院と比較して非常に長かったことがGHCのベンチマーク分析からわかり、改善につなげることができました。
相馬理人さん 急性期病院として、緊急手術の受け入れ態勢を整備することと同時に、“準”緊急手術に対するポリシーを定義し、遵守していく取組みは必須であると思います。それは医療の質にもかかわる部分ですね。
久高弘志先生 その通りです。GHCの分析結果からこうした事実が少しずつわかり、手術室の運用方法を見直すことが、手術件数を増やすだけではなく、医療の質の向上につながるということを医療スタッフが自覚していきました。その結果、看護師をはじめ院内のスタッフもだんだん協力的になってきました。
ー 今後はどのような院内改革を実現していきたいのでしょうか。久高 まずは、手術件数を増やしていきたいと考えています。現在、年間3,300件ほどですから、年間で4,000件くらいにはしていきたい。これは、当院の病床数470床からすると、決して無理な数字じゃないと思っています。そして手術件数を増やすことによって、1日あたりの患者さんの単価もあげていきたいです。相馬 患者単価をあげることは病院経営の安定化にもつながっていくと思います。那覇市立病院は、2010年10月に地域医療支援病院の認定を受けていますが、これも病院経営にはプラスに働いていますね。
久高弘志先生 地域医療支援病院の承認を受けたことによって年間1億円くらいの純利益がでました。地域医療支援病院になれた理由のひとつとして、事務職員の民間採用があります。最近も事務職員を幹部候補生として、民間から5名採用しました。地方独立行政法人化のメリットを活かし、今後は、公務員の数をもっと減らし、違う領域の人材を積極的に採用することによって、医療人では見えない視点から病院の改善を図っていきたいと考えています。現在、7、8年後の完成を目処に新病院の建築がスタートしていますが、地方独立行政法人としてコストの優先順位などを考慮し、建設計画を進めていきたいと考えています。まずは民間病院がどのくらいのコストをかけて建設しているかなどを調査していく予定です。
ー 民間の力を取り入れて、那覇市立病院は、これからどんどん変わっていく予感がします。
久高弘志先生 那覇市立病院がある地域は、二次医療圏の競争が激しい場所です。そうした地域のなかで急性期病院として生き残り、良い医療を安定的に継続して提供し続けるためにも、常に組織改革をし、病院経営に対する意識を持ちたいと思っています。同時に、那覇市の医療行政をバックアップしながら、公立病院としての使命も果たしていきたいと考えています。
地方独立行政法人 那覇市立病院
〒902-8511 沖縄県那覇市古島2丁目31番地1
Tel 098-884-5111
http://www.nch.naha.okinawa.jp/index.jsp
| 広報部 | |
 | 事例やコラム、お役立ち資料などのウェブコンテンツのほか、チラシやパンフレットなどを作成。一般紙や専門誌への寄稿、プレスリリース配信、メディア対応、各種イベント運営などを担当する。 |
Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.