-
Services
Hospital Management - Consulting Services
Publications
- Our Consultants
- Case Studies
- About Us
-
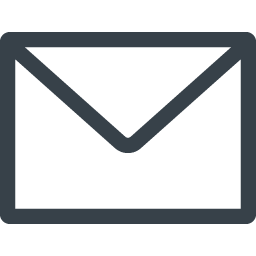
2015年09月30日
| 病院名 | 聖フランシスコ病院 | 設立母体 | 民間病院 |
|---|---|---|---|
| エリア | 九州地方 | 病床数 | 206 |
| 病院名 | 聖フランシスコ病院 |
|---|---|
| 設立母体 | 民間病院 |
| エリア | 九州地方 |
| 病床数 | 206 |
| コンサルティング期間 | 7年間 |
病院ダッシュボードを用いた具体的な取り組みとしては、在院日数短縮と入院期間II超割合の減少、入院栄養食事指導料など出来高指導料の増加などを行いました。
一つ目の取り組みである在院日数の短縮は、内科系パスを作成することで進めました。「長崎クリティカルパス協議会」が2015年3月に発足したことがきっかけです。同協議会の目的は、長崎での各医療機関のクリティカルパス利用を活性化させることです。まず、パスの価値を正しく理解した上で、それぞれの病院でのパス普及を図り、各病院の運用を活性化した上で、質の高い地域連携パスを地域全体で運用しようというものです。今後は、電子化して長崎県の地域医療ネットワーク「あじさいネット」上での運用を想定しており、まずは長崎市内の医療機関に案内しています。
また、日本クリニカルパス学会などでも「DPC病院は、すべての疾患でパス運用できるはず」としているものの、当院ではパス運用ができていない疾患もあったため、DPC病院としての基本に戻ることとしました。
そこで、病院ダッシュボードのケース分析の中にある呼吸器内科の誤嚥性肺炎を活用。通常のパス委員会とは別に、「誤嚥性肺炎パス作成プロジェクト」を立ち上げて作成することとしました。病院ダッシュボードで調べていくと、誤嚥性肺炎の期間II超の割合は、かなり高く、抗生剤物質の使用金額と使用日数は、ベンチマークするとおおよそ全国平均でしたが、使用日数にバラつきがあることが確認できました。
後発医薬品の使用割合については、全病院では平均以上だったのですが、誤嚥性肺炎に限ると、全国平均を下回っていました。さらに、薬剤ごとに使用量や使用日数、医師ごとに使用状況を見ていくと、ここでもバラつきがあることが分かりました。検査の段階では大きな問題は見受けられませんでした。
以上を踏まえて誤嚥性肺炎のクリティカルパスを作成。入院期間は16日とし、抗菌薬の使用は3種類(SBT/ABPC、PIPC、MEPM)に限定(2015年9月末現在はさらに2種類に限定)、検査は入院初日、4日、8日、12日の実施とすることとし、抗菌薬使用期間も4日検査で継続使用か否かの評価をすることを徹底。初日に「嚥下機能評価・リハビリ」を明記し、褥瘡が発生しやすいベッドの角度についても「10度~30度」と明記しました。また、電子カルテの機能を活かし、指定抗菌薬使用届けなどの関連文書を紐付けることにもしました。
これらの取り組みにより、入院期間I、IIの割合が少しずつではありますが、増加しつつあります。さらに、呼吸器内科だけではなく、この増加傾向は全科で示されています。
DPCケースごとの特別食やリハビリなど出来高項目の検証でも活用しています。
入院栄養食事指導料の算定率は、電子カルテを導入したことで、2014年2月頃から上昇傾向にあったのですが、同年6月にNST専任のため管理栄養士が1人減となったことで減少傾向にありました。2015年に入ってからさらに下がり、検証すると管理栄養士は指導こそしているものの、それが対象外の患者だったり、地域包括ケア病棟での指導のため算定できていなかったりしていることが分かりました。従って、入院中2回の算定を目標にすることとしました。
病院ダッシュボードの「チーム医療Plus」であれば、加算に関する算定率などが簡単に確認できるようになっているので、こちらのデータを見れば、現場の人も成果が分かりやすいと思っています。
聖フランシスコ病院
住所:〒852-8125 長崎県長崎市小峰町9番20号
http://www.sfh.or.jp/
●病床数:208床[一般病床176床(緩和ケア22床)、地域包括ケア32床]●標榜科目:内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、外科、呼吸器外科、整形外科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科
| 広報部 | |
 | 事例やコラム、お役立ち資料などのウェブコンテンツのほか、チラシやパンフレットなどを作成。一般紙や専門誌への寄稿、プレスリリース配信、メディア対応、各種イベント運営などを担当する。 |
Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.