-
Services
Hospital Management - Consulting Services
Publications
- Our Consultants
- Case Studies
- About Us
-
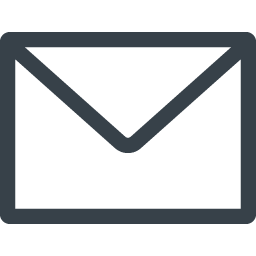
2025.08.01
第61回日本周産期・新生児医学会学術集会(会長・奥山宏臣=大阪大学小児成育外科教授)が2025年7月13~15日に大阪で開かれ、シンポジウム「周産期医療の質と安全の向上のための研究(INTAC研究)~振り返りと今後の展望~」(座長は東京医療保健大学大学院の楠田聡臨床教授(新生児臨床研究ネットワーク理事長、杏林大学医学部小児科専修医)、国立成育医療研究センター新生児科の諫山哲哉診療部長)が15日に開催されました(2025年8月31日までの本学会参加者向けオンデマンド配信サイトはこちら)。「INTACT(インタクト)」の略称で知られる極低出生体重児の予後改善を目指した介入研究について、その意義と成果を改めて検証。INTACTの取り組みでは施設間のアウトカムの差へアプローチする方法論の確立を目指しましたが、ほかの治療領域への応用のほか、自律的な改善組織への発展など副次的な影響も見られました。キーワードはこれまでの医療の危機でも着目されてきた「第三者の介在」「患者中心」「チーム医療」にあるようです。

フォローアップ率9割
INTACTの正式名称は「Improvement of NICU practice and Team Approach Cluster randomized controlled Trial」。日本の周産期母子医療センター・新生児集中治療室(NICU)を有する40施設に、医師・看護師を対象とした包括的な医療の質向上プログラムを提供することで、極低出生体重児(出生体重1500g未満)の予後(3歳時)が改善するかどうかを検証した多施設共同研究です。

早産児を対象とするハイリスク児の管理において、日本は諸外国と比較して高い生存率が報告されています。ただ、死亡退院率を指標とする治療成績に大きな施設間格差があり、治療内容にも施設間差が存在していました。そこで周産期医療母子センターの診療行為を標準化することで、ハイリスク児である極低出生体重児の予後が改善するかどうかを検証しました。検証はクラスターランダム化比較試験にて2011年から実施しました。
INTACTは多くの施設、臨床医、研究者の協力の下で実施されたため、知名度は高く、小児・周産期の領域では大きな話題となりました。2024年2月には蘭エルゼビアが発行するヒトの早期発達を扱う学術専門誌「Early Human Development」に論文「Impact of comprehensive quality improvement program on outcomes in very-low-birth-weight infants: A cluster-randomized controlled trial in Japan」(邦題:極低出生体重児のアウトカムに対する包括的医療の質向上プログラムのインパクト-日本におけるクラスターランダム化比較試験-)が掲載されました。
シンポジウムでは、はじめにINTACTを立ち上げた楠田氏、続いて論文の筆頭著者を務めたグローバルヘルスコンサルティング・ジャパンのコンサルタント(アシスタントマネジャー)で小児科医の西田俊彦が登壇。それぞれ今回のプロジェクトの背景、介入の詳細、結果概要を説明しました。今回のプロジェクトでは、診療ガイドラインの活用のほか、▼現地でのワークショップ開催▼ローカルリーダーの育成▼監査とフィードバック等の要素を組み合わせた医療の質向上プログラムを開発――などPLA(Participatory Learning and Action:参加型学習行動)の手法を導入。介入群19施設にはPLAを含むこれらすべてを提供し、対照群21施設は診療ガイドラインのみを提供しました。
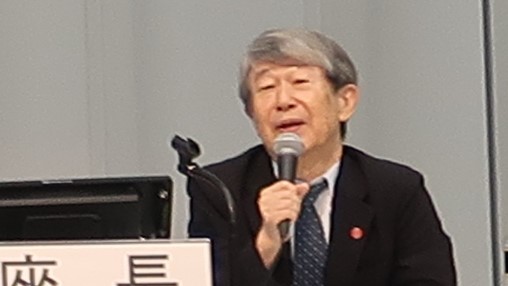
結果、いくつかの臨床上の指標(敗血症や副腎不全の発症低下、輸血回避、経腸栄養確立までの日数短縮など)で介入の効果を認めたものの、「3歳時の神経学的異常なし・生存」という指標では有意差を認めませんでした。ただ、フォローアップという点では9割近いフォローアップ率を実現しました。
楠田氏は今回のプロジェクトを通じて、「日本の新生児医療の優秀性が改めて証明された」と指摘。西田はINTACTの今後の展望について、「同じプロジェクトをもう一度やるということではなく、今後は参加施設がベンチマークで自病院と他の違いを常に明確に意識することが重要」とベンチマークの重要性を訴えました。

7割の施設が活動を継承中
続いて登壇した静岡社会健康医学大学院大学の佐々木八十子講師(公衆衛生・疫学)は、INTACT の対象施設に対して2024年6~9月に実施したアンケート結果を報告。対象40施設中36施設からの有効回答を得ており、佐々木氏は「研究から12年の時を経てなお高い回答率に驚いた」としています。

アンケートでINTACTの活動の継承状況について聞いたところ、68.4%が「受け継がれている」と回答。具体的には、「データに基づく治療方針の決定」「多職種での取り組み」などが受け継がれていることが明らかになりました。INTACTの活動を通じて、院内の医療スタッフ間での対話や振り返りの習慣が浸透し、話し合いをするための仕組み作りのきっかけにもなりました。多くの施設でINTACTの活動が継承されていることについて、佐々木氏は「振り返りと情報共有がカギになったのではないか」とコメントしました。
二次解析で複合急性期合併症予防の可能性が示唆
INTACTにおけるもう一つの直近の活動として、二次解析の実施があります。INTACTでは従来のデータベース以上の粒度で診療プロセスや診療チームの情報を患者情報とセットで収集したため、さまざまな切り口でのアウトカムへの寄与を検討できるデータセットを構築しました。二次解析については、神奈川県立こども医療センター新生児科の豊島勝昭部長(周産期医療センター長、臨床研究所副所長)が登壇して報告しました。

二次解析は2025年に実施。在胎22~24週の超早産児における敗血症、肺出血、循環不全の発症率は、介入群の方が有意に低く、PLAに基づく今回のプログラムが、生育限界に近い早産児の複合急性期合併症を予防する可能性が示唆されました。在胎25~27週の早産児では介入群における急性期合併症のない救命率が高いことも分かりました。豊島氏は「INTACTにおいて改善行動計画を主体的に立案・実行する効果を確認できた意義は大きい。PLAの手法が世界の新生児医療や集中治療領域に応用できることを示したほか、近年普及したオンライン会議システムなどを活用すれば全国規模の施設間の相互支援を実現できる道筋をも示した」としています。
生存率34%から78%、参加施設から「INTACTはIMPACT」の声
INTACTに参加した施設からの報告もありました。登壇した三重中央医療センター小児科(新生児科)の内薗広匡医長はINTACTに参加した2014年の当時を振り返り、「ワークショップを実施し、自病院のデータが下位群に位置していたことに衝撃を受けた」としました。

INTACT参加後の2015年7月から急性期の呼吸・循環管理、看護ケアを変更。介入前の3年間を「前期」、介入後の3年間を「中期」、中期以降の3年間を「後期」として、IVH(脳室内出血)発生率、IVH以外の急性期合併症発生率などを分析しました。結果、在胎28週未満児のIVH発生率は前期57%、中期48%、後期34%。重症IVH発生率は前期24%、中期16%、後期7%で後期は前期に比べて有意に低下しました。そのほかにも在胎23週未満児の死亡退院が前期15人から後期4人に減少、消化管穿孔発症児の生存率が前期34%から後期78%に上昇するなどしました。
治療方針や看護ケアの変更に伴い、院内のコミュニケーション改善を進め、医師同士および医師と看護師の話し合いが増えたと言います。改善活動の当初、院内の反発もあったようですが、徐々に協力者を増やすことで改善活動は進展。内薗氏は「自分にとってINTACTはIMPACTだった」と評しました。
自律的に改善する組織文化とは
最後に座長の楠田氏とともにINTACTを立ち上げた森臨太郎・現宝塚市長は、東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学准教授だった当時を振り返りつつ、INTACTを通じて見えてきた「自律的に改善する組織文化」の条件について自身の考察を述べました。

森市長が考える自律的に改善する組織文化の重要な要素は、(1)より効果的で精緻なフィードバック(2)第三者が介在しつつ当事者主体(PLA)(3)ともに学び合う仲間(実践共同体)――の大きく3つです。中でも(2)のPLAに第三者が介在することの重要性を強調しました。病院経営コンサルティングの現場でもこの「第三者」というキーワードは重要で、「第三者のコンサルタントだから改善の方法や方向性に耳を傾けてみようと思った」「第三者のコンサルタントを通じて院内では言いづらいことを言ってもらえた」などの声はよく聞こえてきます。PLAの「参加型」という良さをより効果的に引き出し、自律的に改善する組織文化を醸成するには、一つの組織の中だけで完結するのではなく、第三者の介在が有効に機能するのかもしれません。
シンポジウムでは会場からの質問も相次ぎ活発な議論が展開され、終わり際には会場から「『患者中心』『家族参加型』の重要性についてどう考えるか」という投げかけもありました。その重要性に複数の登壇者たちが賛同。その流れを経て、今回のシンポジウムの総括を促された森氏は、「これまでも医療の危機的な状況においては、最終的に『患者中心』『チーム医療』のキーワードに行き着き、いくつもの危機を乗り越えてきた。厳しい病院の経営環境や財政難が指摘される今こそ、『患者中心』『チーム医療』のキーワードに立ち返り、その姿勢を病院の中心に持ち込み、経営を改善してもらうのが次のステップ」として会を締めくくりました。
| 西田 俊彦(にしだ・としひこ) | |
 |
コンサルティング部門アシスタントマネジャー。医師、小児科専門医、公衆衛生学修士、経営科学修士。東京医科歯科大学医学部医学科卒業。神奈川県立こども医療センター等を経てGHC入社。臨床・研究活動の経験を生かし、現場視点での改善提案を得意とする(詳細はこちら)。 |
Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.